尊敬する人というのが僕にも何人かいて、
そのうちの一人が、原田正純先生です。
熊本大学医学部で水俣病患者を診療され、
胎児性水俣病を発見されました。
その先生が昨日亡くなったそうです。
僕が阪大歯学部の学生だったときに、医学部歯学部共通の
特別講義に来てくれて、その熱いハートの講義にとても感激したのを覚えています。
水俣病なんて遠い昔のお話のように扱われがちですが
現在と地続きなんだということが、彼の講義から実感しました。
福島第1の事故のあとのいろいろなことが
水俣病のときに起こっていたことと同じように思えます。
参考)
<水俣病>ほんとの空へ・お~い福島:水俣病で得た教訓=大島透
現在からならば、水俣病のときの社会の動きを俯瞰的に見ることができます。
そのときに、何が正しく何が間違っていたのか誰がどうするべきだったかは、きっとコンセンサスが得られるのではないかと思います。
それはきっと、時間的空間的な距離が、社会の物事の判断には必要なんだということなんでしょう。
そのような俯瞰的な視点、歴史的な視点、人類学的な視点を、現在われわれが直面している問題を考えるうえで、持つことは大切なんじゃないかなと思います。


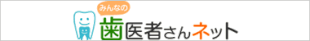
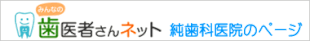


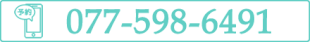


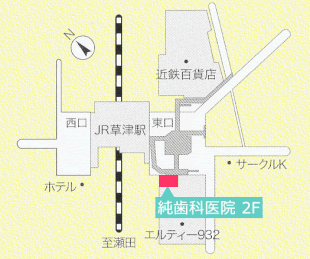
コメントをお書きください